2023年は、Chat GPTやAIコスプレイヤーといった人工知能(AI)が取り沙汰された年になりましたが、この一年で「生成系AIツール」は100種類を超える多種多様な生成ツールがリリースされています。
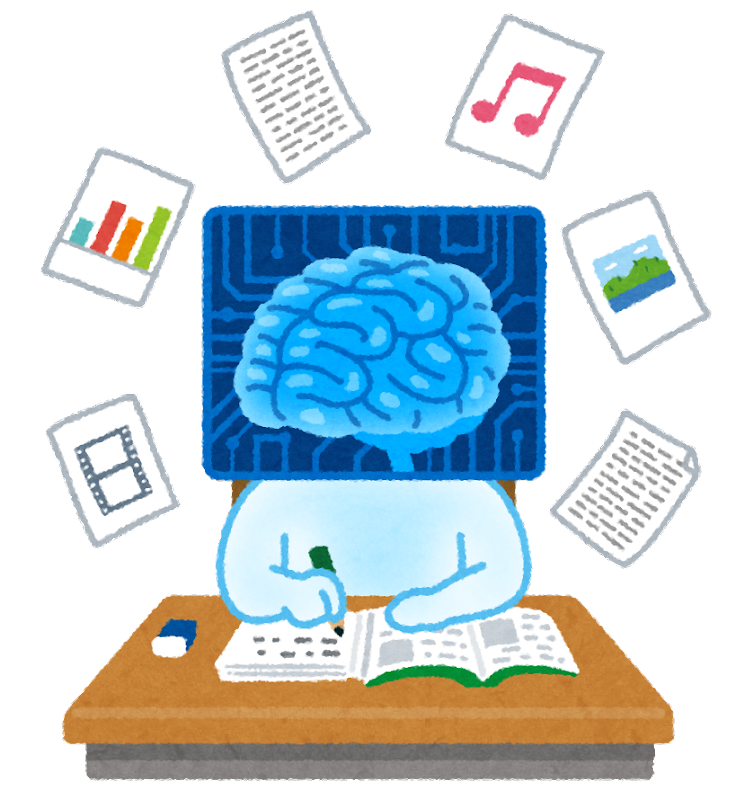
AI生成ツールは「画像」から「動画」へ
ある調査によると生成AIがこの一年で生成した画像は、約150億枚。これは人類が150年かけてようやく到達できた枚数に相当するそうです。AIは休みなく動いてくれますし、学習や成長のスピードも桁違いに凄いです。最近ではノーコードで手軽にAI画像を生成できるツールも増えてきました。ハイスペックなパソコンがなくてもスマホアプリでサクッと画像を生成することもできます。今後も更に手軽でスピーディーに画像生成ができ、AI画像がもっと身近なものになってくるでしょう。
そんなAI業界ですが、今後のトレンドは「画像」から「動画」へシフトしていくと思います。既に動画生成のツールにオープンポーズのような生成ツールも存在しますが、残念なことに今は全く使い物になりません。今後、これらの上位互換された動画生成ツールがリリースされると予想します。
2024年は「動画の年」になりそうなので今後の動向が楽しみですね。


AIコスプレイヤーがバズった頃は「これ、マジすげぇ!」と感動したものですが、AI画像も日々どんどん進化していっておりその学習スピードは目を見張るものがあります。今後のAI画像の進化にも目が離せません。

AIを活用した「広告」
ニュースなどでAI技術を利用した広告が取り上げられていましたが、実在するタレントや俳優を使わないのはなぜなのでしょう?
AI画像と現実の人間は、見分けられないくらい精巧か?と問われれば、AI画像はまだ発展途上の段階で未熟な面の方が目立ちます。では、企業の目的はいったいどこにあるのでしょうか?
考えられるメリット
・コストが安価(タレント、俳優の契約金に比べて格安)
・リスクマネジメント(AIであるため不祥事が発生しない)
・新しい技術であるためメディアに取り上げられやすい(多様なメディアで拡散される)
やはり広告は、多くの人に見てもらうことが目的ですので「※このCMは、AI技術を使用しています。」と耳にすれば、思わず手を止めて見入ってしまうという人は少なくないはずです。
また、先進的な技術をいち早く取り入れるということによって「経営のスピード感」や「風通しの良い社風」を想像させる「ブランディング効果」、「イメージ戦略」という側面もあり、まさに一石二鳥と言えます。「AI技術を使用した広告」というのはプロモーションにおいて、「有能なツール」なのです。

AI技術による広告をした主な企業(商品)
・伊藤園のおーいお茶CM
・キンチョーのキンチョールのCM
・コカコーラ社のキャンペーン
・オタ恋(マッチングアプリ)
写真は「撮る」時代から「生成」する時代へ
この一年間でたくさんの「AI画像」を生成してきましたが、「AI画像」の進化のスピードには本当に驚かされます。そこで考えさせられるのは、「写真」の未来についてです。
「写真」を撮るということに関しては、これまでどおり、趣味や旅行など娯楽としての楽しみ方があり、これからもカメラを手放すようなことはないでしょう。
しかし、ビジネスのシーンとなると「写真」は「AI画像」が取って代わることになるのは確実だと思います。これほどまでに「簡単で手軽に誰でも画像を生成することができる」となると、どうあがいたってコスト面で「AI画像」に太刀打ちすることはできません。現時点ではそこまでビジネスのシーンで多用されていないと思いますが、今後は余程のことがない限り、「AI画像」が代替することになるでしょう。
では、「写真」は「価値の無いもの」になるのでしょうか?
答えは、「ノー」です。そもそも「AI画像」と「写真」は全くの別物と考えるべきです。
旅行、運動会、結婚式、友達との家族との大切な思い出の記録は、「写真」でなければなりませんし、「写真」でなければ意味を成しません。そう言った意味で「写真」は今後もなくなりません。
よくプロカメラマンやグラビアアイドルが「AI技術」によって仕事を奪われるかも知れないという話を耳にしますが、「AI技術」によって仕事が奪われるのではなく、「AI技術」で代替できる程度の仕事しかできないのは、そもそもプロ失格でありプロとは呼べないのです。
写真で何かを表現する場合、写真の持つ「魅力」や「価値」を高められるかがより一段と重要になってくることでしょう。人間にしか表現できないことに「魅力」や「価値」はあるような気がします。
人の心が動く写真は、人しか撮れないのです。
AI技術における2024年の課題
2023年はopenAIを筆頭にAIシステムの開発競争が激化し、多種多様な生成AIツールが誕生しました。AI技術が社会生活に本格的に実装された年でもあり、「AI×ビジネス」が躍進した年とも言えますが、一方で、現状を見るとまだまだAIが生活インフラに根付いているかというと発展途上にあると言えます。
世界のAI市場規模は約20兆円規模まで成長していて、当面も2030年までは緩やかなに加速度的成長が予測されており、市場規模は2030年までに約20倍にもなると言われています。
世界的にはAIバブルの真っ只中にある反面、日本はAI技術の導入や変化への対応が遅れていると言われています。
「AIを1年以内に導入する」とした日本の企業は18%で先進10カ国、最下位。日本が遅れている理由はいくつか挙げられていますが、「AIの導入をリードできる人材がいない」、「AIに関する知見のある人材がいない」という言わば、「AI人出不足」に陥っているという何とも皮肉な現状に置かれています。
2024年問題と言われている「物流問題」や長きにわたり社会問題となっている「少子高齢化」などに直面している我が国の問題解決には「AI技術」が必要不可欠であり、この「AI技術」を駆使し、乗り越えなければならないことは明白です。
情報セキュリティ上の問題や法整備等様々な課題が山積していますが、スピード感をもって取り組んでいくことが急務です。

コメント